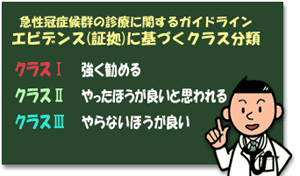
同じ病気の治療を受ける時でも、各病院や各医師の個人的な経験や考えよって治療法が大きく異なる場合がありました。現代の医療においてはエビデンス(証拠)に基づいた治療法の選択が重要視されています。疾患別に治療法選択のガイドラインを策定し医療の内容を標準化する試みが積極的に行われています。
循環器領域においても診療ガイドラインが策定されています。平成11年に厚生労働省医療技術評価総合研究事業として「心筋梗塞の診療エビデンス集」が報告されました。さらに平成14年には日本循環器学会と関連学会から「急性冠症候群の診療に関するガイドライン」がまとめられました。急性冠症候群とは急性心筋梗塞と不安定狭心症という病気を合わせた病態を示す言葉です。このガイドラインでは治療法の選択のもとになるエビデンスの確度に従ってクラスIからクラスIIIまでに分類しています。以下にその分類の定義を示します。
エビデンスに基づくクラス分類の定義
| クラスI | 手技、治療が有効、有用であるというエビデンスがあるか、あるいは見解が一致している |
| クラスII | 手技、治療が有効、有用であるというエビデンスあるいは見解が一致していない |
| クラスIIa | エビデンス、見解から有効、有用である可能性が高い |
| クラスIIb | エビデンス、見解から有効性、有用性がそれほど確立していない |
| クラスIII | 手技、治療が有効、有用でなく、ときに有害であるというエビデンスがあるか、あるいは見解が広く一致している |
急性心筋梗塞の治療の中心は再開通療法
再開通療法とは
急性心筋梗塞とは、冠動脈が閉塞することにより心筋に栄養と酸素がいかなくなり壊死することによって起きる病気です。壊死に陥った心筋は収縮する力がありませんから心臓の働きが悪くなります。しかし、閉塞部よりも末梢の冠動脈によって養われている心筋がすぐに全部壊死してしまう訳ではありません。血液の供給が絶たれた部分の心筋が完全に壊死するには時間がかかります。この一部は壊死に陥っていても、他の部分が完全に壊死していない時間内に冠動脈の血流を回復させるのが再開通療法です。血液の供給を再開させることによって、そのまま閉塞したままにしておけば壊死する心筋を助けることができるのです。発症から12時間以内に行なうと効果が高いことが証明されています。この再開通療法を迅速かつ確実に達成することが急性心筋梗塞の治療の鍵です。
再開通療法の手段にはカテーテル治療と血栓溶解療法の2種類がある
急性心筋梗塞は冠動脈内の動脈硬化部位に血栓が生じて閉塞することが原因です。
血栓とは血液の固まりのことですから、この血液の固まりを溶かして流れを回復させるのが血栓溶解療法です。組織プラスミノーゲン・アクチベータという薬物が多く用いられています。カテーテル治療は閉塞部をバルーンで拡張し、さらにステントと呼ばれる筒状の金網を植込んで血管の内腔を確保し血流を直す方法です。しかし、このカテーテル治療を行なうには実施可能な設備のある病院で、その技術に熟達した医師が行なう必要があります。
現状では、日本の多くの病院では血栓溶解療法ではなくカテーテル治療が選択されています。これはカテーテル治療の方成功率が高く確実に再開通できるからです。

ガイドラインに従った急性心筋梗塞の治療法選択の概要
| カテーテル治療を実施可能な施設でカテーテル治療による再開通療法の適応 | ||
| クラスI (強く勧める) |
発症から12時間以内の患者 | |
| 発症から12時間を超えていても胸痛が続く患者 | ||
| 発症から36時間以内で心原性ショックの患者(心臓の働きが悪く血圧が維持できない状態) | ||
| クラスII (やったほうが良いと思われる) |
血栓溶解療法の禁忌があるが、再開通療法の適応のある患者 | |
| クラスIII (やらない方が良い) |
発症から12時間を超え症状がない場合 | |
| カテーテル治療の経験、技術の乏しい術者が行なう場合 | ||
| カテーテル治療を実施不可能な施設で血栓溶解療法による再開通療法の適応 | ||
| クラスI (強く勧める) |
発症から12時間以内で75歳未満の患者 | |
| クラスII (やったほうが良いと思われる) |
発症12時間以内の75歳以上の患者 | |
| 発症から12時間から24時間の患者 | ||
| クラスIII (やらない方が良い) |
発症から24時間を超え症状のない患者 | |
| 出血傾向があるか、最近手術や外傷の既往のある患者 | ||
■正式のガイドライン(参考)
| 急性心筋梗塞へのカテーテル治療の選択指針 | |||
| クラスI | 1 | ST上昇または新たに生じたと考えられる左脚ブロックが認められる急性心筋梗塞患者で、発症12時間以内あるいは虚血症状が持続する場合は12時間以降でも、梗塞責任血管の形成術が可能な場合、ただし、PCIに熟練した医師が適切な施設環境で行なう場合とする。 | |
| 2 | 急性ST上昇/Q波梗塞または新たな左脚ブロックを伴う発症36時間以内の患者で、心原性ショックを呈し、ショック発症後18時間以内にPCIが実施可能な75歳未満の患者 | ||
| クラスIIa | 1 | 血栓溶解療法は禁忌だが、再灌流療法の適応が考えられる患者に、再灌流療法として実施 | |
| クラスIIb | 1 | ST上昇は認められないが、梗塞責任冠動脈の灌流低下(TIMI grade 0~2 )が認められる急性心筋梗塞患者で、発症12時間以内にPCIが実施可能な場合 | |
| クラスIII | この分類は以下に該当する急性心筋梗塞患者に適応される | ||
| 1 | 急性心筋梗塞発症時に非責任冠動脈に行う待期的PCI | ||
| 2 | 発症12時間を超え、心筋虚血所見のない場合 | ||
| 3 | 厚生労働省の定める施設基準を満たさない場合で、PCI経験の乏しい術者が行うPrimary PCI/Stent | ||
| 急性心筋梗塞への血栓溶解療法の選択指針 | |||
| クラスI | 1 | ST上昇(隣接する2誘導以上において0.1mV以上の上昇)を有し、治療まで12時間以内の75歳未満の患者 | |
| 2 | 脚ブロックのためSTの分析が不明確であるが、急性心筋梗塞を示唆する病歴のある患者 | ||
| クラスIIa | 1 | ST上昇を有する75歳以上の患者 | |
| クラスIIb | 1 | ST上昇を有し、治療まで12~24時間経過した患者 | |
| クラスIII | この分類は以下に該当する急性心筋梗塞患者に適応される | ||
| 1 | ST上昇を有し、治療まで24時間以上経過した、虚血による疼痛が消失した患者 | ||
| 2 | ST低下のみ | ||
| 3 | 血栓溶解療法の絶対的、相対的禁忌の患者
|
||