 子宮がんは子宮の出口(頸部)に出来る子宮頸がんと奥のほう(体部)に出来る子宮体がんに分けられます。
子宮がんは子宮の出口(頸部)に出来る子宮頸がんと奥のほう(体部)に出来る子宮体がんに分けられます。
ここでは子宮体がんについてご説明します。
【子宮体がんの特徴】
子宮体がんは子宮の奥の方、体部に発生する癌で、最近、わが国で増えているがんの一つです。増えている理由として考えられているのは女性の肥満、食生活の変化などです。中高年の女性に多い病気で特徴的な症状として、不正出血があげられます。閉経期前後の女性で不正出血を見た場合、なるべく早く、産婦人科を受診することをお勧めします。
子宮体がんは女性ホルモンの一つであるエストロゲンの影響を受けるものと、エストロゲンと無関係のものがありますが、大部分の子宮体がんがエストロゲンの影響を受けるものと言われています。女性の生理の期間が長くなった、妊娠をしないで長期間エストロゲンの分泌が続く、生理不順でエストロゲンの分泌が長い、肥満の場合、脂肪組織から分泌されるホルモンの影響でがエストロゲンの分泌が高くなった等の現象がわが国の女性に近年、多く見られる事が、子宮体がんが増加している原因といわれています。乳がんの術後に服用を勧められるお薬の中で、エストロゲンの分泌増加作用のあるものがあり、このような薬剤を服用する場合は体癌の検診が必要といわれています。
また一般的に癌検診で子宮がん検診と言えば頸部の検診を指しますので、不正出血があり、体部等での検診を希望される方は、特別に申し出ることが肝要です。
子宮体がんのリスク要因
- 閉経年齢が遅い
- 肥満
- 出産歴がない
- エストロゲンの単独使用
- 乳がん治療に用いられるホルモン剤
【子宮体がんの症状】
子宮体がんでは、ほとんどの場合出血があります。特に閉経前後の長く、少量続く出血は要注意です。
検診で「子宮がんの検査」という場合は、子宮頸がんのみの検査を指す場合がありますので、検査を受ける場合は確認してください。
【子宮体がんの治療】

子宮体がんも頸がんと同様、超音波検査、CT,MRI等で病気の広がり(臨床進行期)を確認することが先決です。その後、手術療法、抗がん剤療法、放射腺療法等が単独、あるいは併用で用いられますが、子宮体がんでは手術療法による子宮摘出が原則であり、頸がんにおける円錐切除のような子宮温存手術が行われることはまれです。近年、子宮体がんに対して有効とされる薬剤(タキサン、大量プロゲストロン)が認可されたことより、抗がん剤治療を組み合わせることにより、従来は治療出来なかった場合でも手術ができたという報告もされるようになりました。
進行期別の標準的な治療法

- 子宮体がんI期
- 癌組織が子宮体部に留まっている場合をI期とし、粘膜内に留まり、筋層内に浸潤していない場合をIa期、筋層に浸潤しているが1/2以内に留まっている場合をIb期、筋層の1/2を超えて浸潤している場合をIc期と言います。I期の場合、基本的には手術による子宮全摘が基本ですが、Ib期、Ic期の場合は骨盤内リンパ節あるいは旁大動脈リンパ節の摘出を追加することもあります。手術により、摘出した子宮の病理学的な検査の結果、ハイリスクと診断された場合、抗がん剤あるいは放射腺治療を追加する場合もあります。

- 子宮体がんII期
- 子宮体部を超えて、頸部まで浸潤している場合をII期とします。頸部内腔の粘膜内に留まっている場合をIIa期、粘膜を超えている場合をIIb期とします。
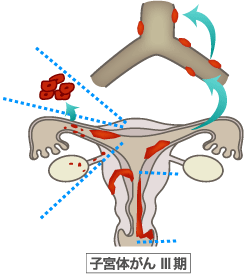
- 子宮体がんIII期
- III期は腫瘍組織が子宮を超えて広がっているが骨盤の中にとどまっている場合、あるいは骨盤内や大動脈周辺のリンパ節に転移を認める場合をIII期といいます。IIIa期は骨盤の中の卵巣、卵管、骨盤腹膜に転移している場合や腹水の中に癌細胞が認められる場合です。IIIb期は膣壁に転移している場合、IIIc期は骨盤内、大動脈周囲のリンパ節に転移が認められる場合です。治療法では、手術療法に加えて、抗がん剤あるいは放射線による手術後の追加治療が行われる場合が多いようです。また手術の場合も骨盤内あるいは大動脈周囲のリンパ節の摘出が行われることが多いと思われます。

- 子宮体がんIV期
- 腫瘍組織が骨盤を超えて、肺等へ遠隔転移している場合、あるいは膀胱、直腸へ浸潤している場合です。従来はIV期の場合、手術は不可能で、抗がん剤の治療が行われる場合がほとんどでしたが、最近は最初抗がん剤を投与、遠隔転移が消失した場合、手術療法を実施する報告も見受けられるようになりました。
若年者体癌
稀に、若い女性に体癌が発生することがあります。
若い女性に子宮体がんが発生した場合、子宮体がんの標準的な治療法は手術で子宮を摘出する方法ですが、まだお子さんがいない女性の場合、この治療法だと赤ちゃんを産めなくなります。このような若い女性の子宮体がんに対して、ホルモン療法により治療をすることが一部では行われています。子宮をとらずに将来赤ちゃんが産める可能性を残すことが目的です。

ホルモン療法は、癌が子宮の内側にだけにとどまって子宮の筋層の中に入り込んでいない場合、高分化型の癌(癌の顔つきが比較的穏やかな癌)の二つの条件を満たす場合に限って行うことが可能とされています。
具体的な治療法は高濃度の黄体ホルモン(プロゲステロン)という薬を4~6ヶ月間内服します。このプロゲステロンというホルモンはエストロゲンに対して拮抗的に働く作用があるので、エストロゲンに依存している、子宮体がんを消失させる作用があるといわれています。
黄体ホルモンによる治療法は、子宮を残すことができる反面、薬が効かなかった場合、病気が進んでしまう可能性があることや、一度癌が消えてもまた出てきてしまう(再発)リスクがあることを十分に理解して治療を受けていただくことが必要です。
以上よりこの治療法は一般的ではありませんが、地球温存を強く希望する方に、リスクとベネフィットを良く説明、同意を得られた後、投与しています。
子宮体がんの予後(新潟大学(1997-2006))
| 進行期 | 患者数(人) | 5年生存率(%) |
|---|---|---|
| I期 | 128 | 94.9 |
| II期 | 13 | 74.0 |
| III期 | 59 | 50.9 |
| IV期 | 21 | 9.5 |