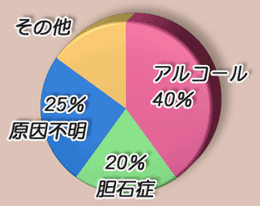
急性膵炎とは膵臓におこる急性の炎症で、膵臓の細胞が傷害を受けて、過剰に産生された悪い物質が肺や腎臓などの他の臓器にも影響を及ぼすことがあります。急性膵炎の原因はアルコール、胆石性、特発性のほか、薬剤、高脂血症、膵臓癌などがありますので、原因をよく調べることが大切です。
**適切な治療をするために、発症48時間以内の重症度判定が重要です。膵臓の傷害の程度によって数日で治る軽いものから、数時間で重篤になるものまであり、発症初期の適切な診断と治療が予後を大きく左右します。重症度判定基準は1998年の厚生労働省特定疾患難治性膵疾患調査研究班で作成された急性膵炎の重症度判定基準と重症度スコアを参照にして下さい。重症急性膵炎は全身管理が可能な医療施設へすみやかに搬送して下さい。
急性膵炎の治療の基本は、絶食による膵の安静、十分な輸液、呼吸・循環動態の維持、痛みの治療、感染症などの合併症の予防です。

| 1.初期の十分な輸液(強く勧める) | |
| 炎症による循環血漿量の低下を補充するために軽症であっても十分な初期輸液を行います。重症例では血圧、中心静脈圧、ヘマトクリット、血清総蛋白濃度や時間尿量(1 ml/kg以上)を指標に輸液量を決定し、循環動態の安定を確保することが重要です。 | |
| 2.経鼻胃管(やらないほうがよい) | |
| 腸閉塞や嘔吐がある場合以外は留置する必要はありません。 | |
| 3.薬物療法 | ||
| (1)鎮痛剤による疼痛対策(強く勧める) | ||
| 精神的不安を除去するためにも、早期より十分な除痛が必要です。軽症から中等症では塩酸ブプレノルフィン(商品名レペタン)を初回投与0.3mg静注、続いて2.4mg/dayの持続静注が疼痛効果に優れています。 | ||
| (2)抗菌剤の予防的投与 | ||
| 重症例では強く勧めますが、軽症例では推奨されていません。 軽症と中等症では膵および膵周囲の感染症の発生頻度が低いので、抗菌剤の予防的投与は必要ありません。しかし、重症では腸内細菌による感染症の合併は死に至るので、膵移行性がよく広域スペクトラムを持つイミペネム(商品名チエナム)などの予防的投与が必要です。 |
||
| (3)重症例に対する蛋白分解酵素阻害剤の大量持続点滴療法(やったほうが良い) | ||
| 軽症、中等症では有用性は認められていませんが、重症例ではメシル酸ガベキサート( 商品名FOY) 2400mg/dayの持続点滴静注を7日間、あるいは900-4000mg/dayを4-12日間投与で有効性が認められています。しかし、実際に保険診療上の用量は600mg/dayまでである点が問題です。メシル酸ナファモスタット(商品名フサン) 20mg/day、ウリナスタチン(商品名ミラクリット) 50000単位はメシル酸ガベキセート(商品名FOY)200mg/dayに匹敵します。 |
||
| (4)軽症と中等症に対するヒスタミンH2受容体拮抗薬(やらないほうがよい) | ||
| H2受容体拮抗薬の直接的な有効性は認められていませんが、急性胃粘膜病変や消化管出血合併例では投与します。 | ||
| 4.重症例における早期から経空腸的な栄養管理(やったほうがよい) | |
| 従来は膵の安静を保つ目的で中心静脈栄養が行われてきましたが、経空腸的な栄養管理のほうが中心静脈栄養に比べて感染などの合併症が減少することが判りました。軽症例では中心静脈栄養は必要ありません。 | |
| 5.重症例での選択的消化管除菌(やってもよい) | |
| 重症急性膵炎の膵および膵周囲の感染症の予防するために、腸内細菌に有効な非吸収性抗菌薬を投与します。 | |
| 6.腹腔洗浄、腹膜灌流(やってもよい) | |
| 腹腔内に貯まった毒性物質を洗浄液で洗い流すと重症膵炎が改善したという報告と、腹膜から漏出する蛋白量が増えて血漿輸注が増加するという報告もあります。 | |
| 7.重症急性膵炎における血液浄化法(やってもよい) | |
| 発症早期の持続的血液濾過透析(continuous hemodiafiltration; CHDF)は、血液中の悪い物資を除去し、腎臓、心臓、肺などの多臓器不全への進行を防止する目的で行われます。また、血漿交換はCHDFで除去できない分子量の大きい物質を除去することができますが、いずれも開始時期や多臓器不全の予防効果は確定されていません。 | |
| 8.壊死性膵炎における蛋白分解酵素阻害薬と抗菌薬の持続動注療法(やってもよい) | |
| 蛋白分解酵素阻害剤(メシル酸ナファモスタット:商品名フサン)と抗菌薬(イミペネム:商品名チエナム)を用いた持続動注療法は重症膵炎の死亡率や感染合併率を改善できる可能性があります。血管造影で動脈内にカテーテルを留置しますので、専門的な技術が必要です。 | |
| 9.胆石が原因の急性膵炎は、内視鏡的治療あるいは外科的治療の適応となります。 | ||
| (1)胆石性膵炎で黄疸などの胆動通過障害や胆管炎の合併がある場合の緊急内視鏡的逆行性胆管造影/乳頭切開術(やったほうがよい)。 重症例で有効ですが、手技による合併症もあるので、専門医のいる施設に依頼して下さい。 |
||
| (2)膵炎が良くなってから同一入院期間中に胆嚢摘出術を行う(やったほうが良い)。軽症の膵炎の場合は合併症がなければ腹腔鏡下胆嚢摘出術でもよい(やってもよい)。 胆石がある場合は膵炎の再発の危険があるので、時間をおかないで胆嚢を除去したほうがよいでしょう。 |
||
| 10.外科的手術 | ||
| (1)発熱や炎症反応の悪化など膵局所の感染の疑いがあれば、CTや超音波ガイド下で穿刺吸引をして細菌がいるかどうかを調べます(強く勧める)。 | ||
| (2)腐った膵臓に細菌が確認されたら(感染性膵壊死)、膵壊死部摘出術などの外科的処置をします(強く勧める)。また、感染が確認できなくても可能性が否定できない場合にも手術をすることがあります(やったほうが良い)。 | ||
| (3)膵壊死部を除去したのち、洗浄用のチューブを留置し、腐った物質がなくなるまで持続的に洗浄します(やったほうが良い)。 | ||
| (4)重症膵炎から約4週間以降にみられる膵臓付近にできる膿の貯留が膵膿瘍です。これに対して外科的あるいは皮膚を介して管を入れて排膿(ドレナージ)をするか(やっても良い)、また、経皮的ドレナージが無効の場合に外科的ドレナージをします(やったほうが良い)。ドレナージで良くならない場合には外科的に治療します。 | ||
| (5)膵炎発症約4週間以降に膵液や組織の融解物が貯留して仮性嚢胞ができることがあります。痛みや嚢胞が大きくなるような場合は経皮的あるいは内視鏡的ドレナージをします(強く勧める)。良くならない時は外科的ドレナージをします(強く勧める)。 | ||